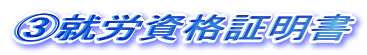1.帰化とは
他国の国籍を取得することを帰化といいます。
2.帰化の種類
①普通帰化(国籍法5条)
②簡易帰化(国籍法6条~8条)
③大帰化 (国籍法9条)
3.帰化の要件
外国人が日本に帰化をするためには、法務大臣の許可を得る必要がありますが、、条件は以下のとおり。
(1)国籍法5条の規定
①居住要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②能力条件:20歳以上で本国法によってにう力を有すること。
③素行条件:素行が善良であること。
④生計条件:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
⑤重国籍防止条件:国籍を有せず、または、日本の国籍の取得によってもとの国籍を失うべきこと。
⑥忠説条件:日本国憲法施行以降において、政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、またはその企てや主張する政党その他の団体を結成しもしくはこれに加入したことがないこと。
⑦日本語の能力条件:日本語の読み書き、会話の能力があること。
(2)国籍法6条の規定
日本国と特別の血縁もしくは地縁関係を有する外国人について第5条の条件を緩和しています。
下記に該当する者で日本国に住所を有する者については、継続5年の居住条件が免除されます。
①日本国民であったものの実子で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。
③日本で生まれた者で、その実父または実母が日本で生まれた者。
④引き続き10年以上日本に居所を有する者。
(3)国籍法7条の規定
日本国民の配偶者たる外国人については、下記条件を満たしているものは第5条の居住条件および能力条件の緩和ないし免除しています。
①日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する場合。
②日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
(4)国籍法8条の規定
国籍法6条、7条の該当者に比べ、さらに日本と密接な血縁関係を有する者については、第5条のうち、国籍の積極的接触の防止を目的とした条件(5号)
国家社会の防衛上の要請に基づく条件(3号、6号)を具備すれば足りるとし、これ以上の住所(1号)、能力(2号)、生計(4号)の各条件は免除される。
①日本国民の実子で、日本に住所を有する者
②日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であったもの。
③日本の国籍を失ったもので日本に住所を有する者。(日本に帰化した後日本国籍を失ったものを除く)
④日本で生れ、かつ、出生の時から国籍を有しないものでその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
(5)国籍法9条による帰化
日本に特別の功労のある外国人については、第5条に規定する帰化の条件を全く具備していない場合でも、法務大臣は、国会の承認を得て、帰化を許可することができる。
4.手続きおよび必要書類
帰化においては、必要書類を作成の上、法務局に申請することになります。
申請から結果が出るまでは約半年から1年近くかかります。
申請書類には、帰化許可申請書、親族の概要、帰化の動機書、履歴書、在勤および給与証明書、宣誓書、生計の概要、事業の概要(給与所得者は不要)
居宅付近の略図等、勤務先付近の略図等が必要になります。(一例)
帰化許可申請は、原則 法務局への本人出頭になります。
当事務所では、初期相談、資料収集、書類作成支援、法務局同行等を行います。
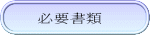
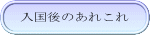
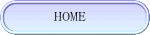
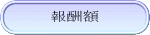
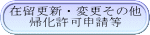
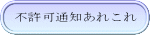
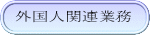
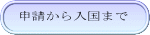
日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更の許可を受ける必要があり、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らでその本来の活動の遂行を阻止しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬をうける活動を行おうとする場合は、資格外活動許可を受けなければならないとされております。なかでも在留資格の「留学」または「就学」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなくし資格外活動を行うことにできる包括的許可を受けられますが、この申請は原則として、教育機関の「副申請」を添えて行うことが必要です。
なお、この包括的許可についても、活動時間や活動場所等の制限があります。
(1)活動時間の上限
・留学生:1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動。
(教育機関の長期休業期間などでは、1日8時間以内)
・専ら聴講による研究生または聴講生:1週について14時間以内の収入を伴う事業を畝いする活動又は報酬を受ける活動
(教育機関の長期休業期間などでは、1日8時間以内)
・就学生:1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動。
(2)活動場所等の制限
風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの、または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事する者を除く。
また、本邦の大学を卒業した外国人であって、在留資格を「短期滞在」をもって在留するものが、卒後前から引き続き就職活動を行う場合は、個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになっております。この申請については、大学が発行する「推薦状」を添えて行います。さらに、在留資格「家族滞在」をもって在留する者についても、週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられる
ようになっていますが、上記と同様の制限があります。
日本にいる外国人が日本から出国すると、その時点で付与されていた在留資格は消滅します。しかし出国が一時的なもの(親族訪問や海外出張など)で、また日本にもどって在留を続ける場合に、再入国許可を得ることで以前の在留資格で在留を続けることができます。再入国許可には、一回限りのものと有効期限内であれば何回でも出入国ができる数次のものとがあります。また、再入国許可を得て出国した場合には、再入国許可の有効期間内に再び日本に入国しなければなりませんが、国外で病気になり期間内に再入国ができないなどの相当の理由があるときは、救済措置(再入国許可の有効期間の延長許可)などがあります。また、再入国許可を取らずに出国した場合は、あらたに一から在留許可を取りなおさなければなりません。
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。これは現在 就労可能な在留資格(たとえば技術、技能など)を付与されている外国人が、現在の勤務先を退職して他の会社へ転職する場合に、新たに勤務する会社での活動に該当するか否かを確認するために行います。なお、現在の在留資格の期限が迫っている場合は、就労資格証明書の交付申請ではなく、在留期間更新許可申請を行います。
1.出国命令制度
冒頭でも触れましたが、不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は、入国管理局身柄を収容の上、退去強制手続きを得て、本国へ強制送還されます。退去強制処分をうけると、5年間(過去に同じ処分を受けたことのある外国人は10年)は、日本に入国できなくなります。
しかし、不法残留外国人が、帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合には、以下の要件を満たすことを条件に、身柄を収容されることなく出国することができます。これを出国命令制度といいます。出国命令制度により出国した外国人は、日本に入港できない期間も1年に短縮されます。
<出国命令の要件>
①速やかに出国することを希望して、自ら入国管理局に出頭したこと。
②不法残留している場合に限ること。
③窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
④これまで強制送還や出国命令により出国していないこと。
⑤速やかに出国することが確実であること。
2.在留特別許可の申立
(1)在留特別許可とは。
在留特別許可とは、日本に在留する外国人が退去強制事由に該当する場合において、日本に在留することを認めるに足りる特別な事情がある場合に法務大臣の裁量により、特別に在留を許可する制度をいいます。
なお、「在留特別許可申請」という申請はしません。あくまで、退去強制手続きの中で、入国警備官による違反調査、入国審査官による口頭審理を得て、法務大臣に対して在留特別の申し立てを行う方法によります。
(2)手続きの概要
①出頭申告
・出頭申告とは、退去強制事由に該当する外国人が自ら地方入国管理局に出頭して、その容疑を申告すること。
・容疑を申告して、早く帰国したい場合と、日本に引き続き在留したい場合とがありますが、早期に帰国する場合は、一連の退去強制手続きを終え、送違要件(旅券、航空券など)が整っていれば速やかに送還先に退去させます。なお、一定の要件を満たす不法残留者は、退去強制ではなく、出国命令の対象になります。また、日本に在留を希望する場合は、退去強制手続きの中で、日本で生活したい旨を具体的に申し立て、在留を希望することができます。特別に認められるかどうかは、最終的に法務大臣の裁量になります。
②入国警備官による違反調査
違反調査とは、退去強制手続きの第一段階であり、退去強制事由に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が行います。
③引渡
入国警備官は、違反調査により容疑者を収容したときは、身体を拘束した時から48時間以内に、調書および証拠物とともに、その容疑者を入国捜査官に引き渡さなければなりません。これを「引渡し」と呼んでいます。
引き渡しを受けた入国審査官は、入国警備官がおこなった違反調査に誤りがないか審査をします。
④入国審査官による違反調査
入国警備官から容疑者から引き渡しを受けた入国審査官は、容疑者が退去強制対象者(退去強制事由に該当し、かつ、出国命令対象者に該しない外国人)に該当するかどうかを速やかに審査します。
容疑者が、それを認め、帰国を希望されるときは退去強制令書が主任審により発付され、その外国人は退去強制されます。
一方、容疑者が認定があやまっていると主張したり、あるいは、誤っていないが、日本での在留を特別に認めてもらいたい時は、第2段階の審査にあたる口頭審査を請求することがでいます。
なお、違反審査の結果結果、その容疑者が退去強制事由に該当しないことがわかり入国審査官がそのことを認定した場合や、入国審査官がその容疑者が出国命令対象者に該当すると認定し、主任審査官から出国命令を受けたときは、入国審査官は直ちにそのものを放免しなければなりません。
⑤特別審査官による口頭審理
入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定した場合で、容疑者が認定があやまっていると主張したり、あるいは、誤っていないが、日本での在留を特別に認めてもらいたい時は、認定の通知を受けた日から3日以内に口頭をもって特別審理官に対し口頭審理を請求し、これに基づき、審理が行われることになります。
これが特別審理審理官による口頭審理です。特別審理官は、法務大臣が指定する上級の入国審査官です。
特別審理官は、入国審査官の行った認定に誤りがあるかどうかを判定します。誤りがないと判定し、容疑者がこれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書が主任審査官により発付され、我が国から退去強制されます。
一方、容疑者が認定があやまっていると主張したり、あるいは、誤っていないが、日本での在留を特別に認めてもらいたい時は、第3段階の審査にあたる法務大臣への意義の申出を行うことができます。また、口頭審理の結果、退去強制事由のいずれにも該当しないことがわかり特別審理官がそのように判定した場合や特別審理官がその容疑者が出国命令対象者に該当すると判定し、主任審査官から出国命令を受けたときは、特別審理官はただちにその者を放免しなければなりません。なお、なお、口頭審理において、容疑者またはその代理人は、証拠を提出し、証人を尋問し、また、容疑者は特別審理官の許可を受けて親族または知人の一人を立ち合わせることができます。他方、特別審理官は、証人の出頭を命じ、宣誓をさせ、証言をもとめることができることとなっています。
⑥意義の申出
入国審査官の認定、そして特別審査官の判定を経て、容疑者が認定があやまっていると主張したり、あるいは、誤っていないが、日本での在留を特別に認めてもらいたい時はその判定を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、最終的な判断をも法務大臣に求めることができる。これが意義の申出です。特別審査官のさらに上級の入国審査官である主任審査官が法務大臣に書類を送付して行います。主任審査官とはもっとも上級の入国審査官の一つで法務大臣が指定します。
⑦法務大臣の裁決
法務大臣は特別容疑者を取り調べることはしませんが、一連の手続きで作成された証拠を、記録をしらべて採決をすることになります。
そして、法務大臣が意義の申出に理由がないと採決した場合は、主任審査官にその旨を通知して主任審査官が退去強制令書を発付することになります。また、法務大臣が意義の申出に理由があると採決したむねの通知を受けたときや容疑者が出国命令対象者に該当するとして異議申出に理由があるとして裁決した旨の通知を受けて出国命令をしたときは、ただちにその者を放免しなければならない。
⑧在留特別許可
法務大臣は、異議申出に理由がないと認める場合でもつぎのような場合には、在留特別に許可できるとされています。
この法務大臣の裁決の特例が、在留特別許可になります。
1.永住許可を受けているとき
2.かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
3.人身取引等により他人の支配下におかれて本邦に在留するものであるとき
4.その法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
(3)仮放免許可申請
①仮放免とは
仮放免とは、収容令書又は退去強制令書により収容されている被収容者について、一定の者からの請求によりまたは職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を解く措置のことをいいます。
②仮放免を請求できる人
被収容者本人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、代理人
③仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容者所長に、また、地方入国管理局の収容場に収容されている場合は、当該収容場を所轄する地方入国管理局の主任審査官に請求します。
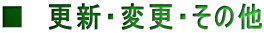

伊関行政書士事務所
永住許可の意義:永住許可とは、。終生日本に在留して差し支えないという法務大臣の許可のことをいいます。
外国人にとっては、永住許可を得ることにより、在留許可更新許可申請から解放されると同時に、在留中の活動に制限がなくなるために在留資格変更や資格外活動の許可申請の必要もなくなり大きなメリットがあります。
ただし、永住許可を得たからといっても、日本から出国する場合には、再入国許可を得る必要があり、その点は注意が必要です。
主なガイドライン:
原則的基準
①素行要件:善良であること。
②独立生計要件:独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③国益合致要件:その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること。
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。(なおこの期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
・納税義務等の公益的義務を履行していること。
・現に有する在留資格について、永住許可申請時点において施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(3年間)を許可されていること。
・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
緩和要件(原則10年在留に関する特例)
①日本人の配偶者、永住の配偶者、特別永住者の配偶者の場合、同居実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上
日本に在留していること。その実子等(特別養子含む)の場合、1年以上日本に継続して在留していること。
②「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
③難民認定をうけた者の場合にあっては、5年以上継続して日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があるとみとめられる者で、5年以上日本に在留していること。
あなたの街の法律家として伊関淳が親切、丁寧にご相談に応じます。
東京都練馬区高松6-22-4
tel/fax 03-6273-1519
在留期間の2ヵ月前から可能(現在付与されている在留期間内に申請を行う。なお、在留期間をすぎてしまった場合は、法律上は不法残留状態にあり退去強制手続きがとられ、外国人自ら入国管理局に出頭し、退去強制手続きの中で在留特別許可を得る必要があります。ただし、不法残留の期間が短期間で、悪意がなく、また、仮に在留期間内に申請が行われていたら許可されていたであろうと認められた場合には、特別に申請を受理して在留期間の更新を許可することがあります。このような扱いを特別受理と呼びます。また、適法に在留期間更新の申請をしたものの期間内に許可、不許可の決定がなされない場合、形式的には不法残留になりますが、実質的な違法性を欠くため罪になりません。その後、許可を受ければ、その許可は旧在留期間に接続されて行われるために不法残留は治癒されます。 また、不許可の場合は、引き続き在留ができないため日本から出国しなければなりません。もし、在留期間をすぎても出国しない場合は、不法在残留なり、退去強制の対象になります。
(補足)
実務上では、在留期間更新が不許可の場合でも、本人が出国の意思がある場合、不許可処分時に在留資格を出国準備のための「特定活動」に変更する在留資格変更許可申請があれば、在留資格を「特定活動」に変更許可して適法状態の下で出国させる運用が行われます。これを「出準の特活」と呼んでいます。
在留資格に該当する状況にあるのか?期間を更新するに値する相当の理由があるのか?等
事業と暮らしの法務アドバイザー
| Copyright(c)2008 伊関行政書士事務所All Rights Reserved. |
現在付与されている在留資格から他の在留資格へ変更する必要が生じた場合には、在留資格変更許可申請をします。たとえば留学生が大学を卒業して日本の企業に就職して働く場合には、「留学」から「他の在留資格(技術など)」への変更をする必要があります。なお、「短期滞在」から「他の在留資格」への変更については、入管法上は特別な事情がないと許可しないとされておりますが、一部の例外を除いて在留資格変更許可申請自体が受理されません。
(例外1)「短期滞在」から「日本人の配偶者等」または、「定住者」などの身分系の在留資格に変更する場合。
(例外2)在留資格認定証明書を取得している場合。
また、卒業すると「専門士」の称号を付与された留学生は、在留資格変更許可申請の場合に限り、「人文知識・国際業務」または「技術」への在留資格への変更を許可する取扱いがされています。なお、一旦出国すると「専門士」の資格は使えなくなります。
在留資格を変更するに値する相当の理由があるのか?等